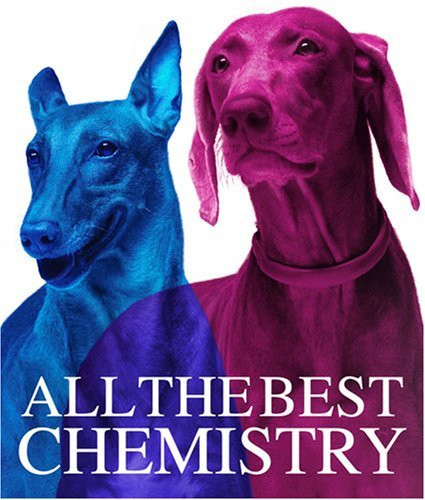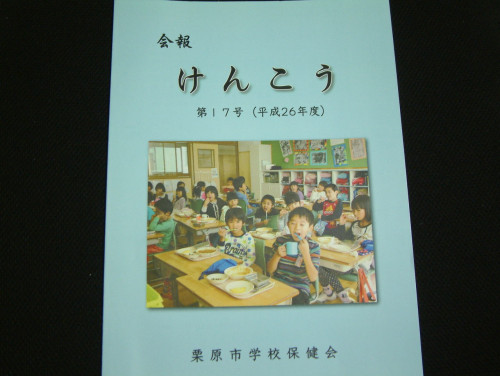院長ブログ
芸術家で発明家
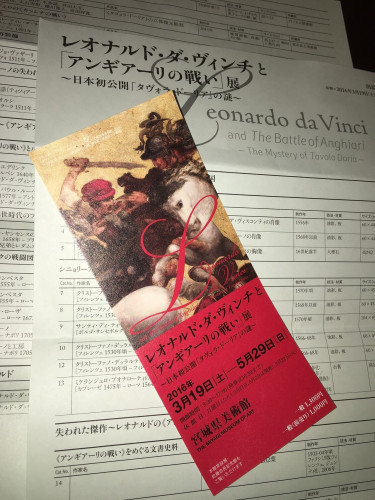 今日は病院の定休診日でしたので、仙台の宮城県美術館でレオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展を見てきました。レオナルド・ダ・ヴィンチの作品と言えば、「モナ・リザの微笑み」や「最後の晩餐」等が有名ですが、それらについてはそれぞれ一枚のコピー画の展示だけで済まされてました。2006年のアメリカのヒット映画、トムハンクス主演の『ダ・ヴィンチ・コード』では「最期の晩餐」にまつわるサスペンスを描いてましたが、それに関するミステリアスな展示があるかも、と思っていただけに肩透かしを食いました。
今日は病院の定休診日でしたので、仙台の宮城県美術館でレオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展を見てきました。レオナルド・ダ・ヴィンチの作品と言えば、「モナ・リザの微笑み」や「最後の晩餐」等が有名ですが、それらについてはそれぞれ一枚のコピー画の展示だけで済まされてました。2006年のアメリカのヒット映画、トムハンクス主演の『ダ・ヴィンチ・コード』では「最期の晩餐」にまつわるサスペンスを描いてましたが、それに関するミステリアスな展示があるかも、と思っていただけに肩透かしを食いました。しかし奥に進むにつれ明らかになったのは、もう憶測でしか計り知れないダ・ヴィンチの幻の一大作品の仰天エピソードだったのです。ダ・ヴィンチは様々な名画を創作し名声を築き上げたのち、1504年にフィレンツェ共和国から政庁舎の大会議室「500人大広間」に『アンギアーリの戦い』を壁画として描くよう依頼されました(相当大きい大作だったみたいです)。しかしダ・ヴィンチが独自の技法にこだわったため壁画は失敗、途中で頓挫し完成をあきらめてしまいました。やがて多くの画家が未完成のこの壁画を模写したものの、約50年後会議室の改装とともにダ・ヴィンチの壁画の上にまったく別の壁画が描かれてしまいました。ですからこの幻の壁画を知る手掛かりはこれを模写した他の画家の作品で想像するしかないと思われていました。
もう一つ感嘆したことは、ダ・ヴィンチは絵画だけではなく、とにかくあらゆる分野で大きな功績を残したのは有名ですが、展示されていた発明品の中で焼肉にまんべんなく火が通る焼肉装置というのがあったことでした。500年前のことです。
諸行無常 生々流転
もう解散してしまいましたが、ケミストリーは今から10年以上前テレビ東京系のオーデション番組で男性ボーカルのコンテストがあり、審査の最後に残った5人から最終的に選ばれた堂珍と川畑の二人で結成されたデュオでした。デビュー当初はヒットを連発しましたが堂珍の結婚を境に人気が急落したような気がします。逆に最終選考の5人に残りながら落選した中にATSUSHIがいました。ご存知のようにやがてEXILEのボーカルとなり現在のような頂点を極めたわけです。またEXILEもツインボーカルですが当初はATSUSHIと清木場俊介でした。清木場は突然脱退、ソロデビュ―をし中嶋美嘉の曲をカバーしたあたりまではよかったのですが、最近は鳴かず飛ばずですね。今のボーカルのTAKAHIROはイケメンでタレント性がありますが,歌唱力がいまいちなところを考えるとやめなきゃよかったのになあとも考えてしまいます。
ケミストリーの曲のタイトルでいえばさしずめ『You Go Your Way』ですかねえ。
外国人観光客は日本の何を見に来ているのか?
さて日本に来た外国人観光客は日本の何を見に来るのでしょう。浅草の仲見世通りでしょうか。京都の伏見稲荷大社の赤い鳥居でしょうか。戦後、日本のイメージと言えば「フジヤマ、ゲイシャ、サムライ」と言われていました。ゲイシャ、サムライはなかなか見れませんがその代わり着物は日本を明確に象徴する服飾文化として一度は見たいと思ってるはずです。
2012年バロンドール(サッカー FIFAの年間最優秀選手)の授賞者は、男子はご存じアルゼンチンのメッシ(バルセロナ)で、女子はワールドカップを制したわがなでしこの澤穂希選手でした。スイスで行われたその受賞式での澤選手はジャパン・ブルーではなく鮮やかな水色を基調とした清々しい振り袖姿で出席しました。名だたるゴッツイ男子選手の中にあって、これが女子サッカー百戦錬磨のあの澤穂希か!とそのあでやかさに誰もがうなったに違いありません。その際、出席した選手や関係者が最も並んで写真を撮りたがったのは、かのメッシではなく振袖姿の澤選手だったそうです。
本来着物は日本の文化を簡単明瞭に表現できるどこでも見られる服飾だったはずです。しかしながら今の日本では着物の存立がますます危うくなってます。先月仙台市の中心部にある老舗の呉服屋さんが店を閉めました。10年前と比べ売り上げが10分の1に減ったそうです。何らかの着物を自前で所有している女性(家庭)は大幅に減少し、人に着付けることのできる人はもちろん、自分で着付けることのできる人も激減しているのが原因でしょう。さらに成人式の着物は華美さが強調される傾向にあり、全てを自前でそろえるのは親の重い負担となるためレンタルのケースが多く、その後の人生でも着物を持たないので着る機会がほぼ皆無になってしまうことがその背景にあるのでしょう。
確かに着物自体セットでそろえるのは金額的にかさむことも大きな問題です。しかし格安な素材の反物やリサイクルも多数存在しますし、値段と格(フォーマルか普段着か)は一致しませんので、格安でもフォーマルな着物をそろえることもできます。また一度そろえてしまえば流行や年齢に影響されにずに長年にわたって着れるのが着物のメリットですし、様々な場面で活躍できるのも大きな魅力です。やはり日本の女性には着物をもっともっと身近に着こなしてもらいたいですね。
外国人観光客から『キモノガミタイデス。』と聞かれて、『着物ねぇ。どこに行けば見られるんだろう?ノーベル賞の授賞式かな…』てなことになってほしくないですね。
東日本大震災は1000年に1度の災害ではなかったのか!?
あの東日本大震災からまだ5年です。わが故郷気仙沼にはやっと災害復興住宅の建設が始まり来年の入居に向け部屋の抽選会も行われたようです。しかし完全な復興の姿にはまだほど遠いままです。震災当時、津波で倒壊した自分の実家や近所の惨状を見て、なんだろう一体これはと現実と記憶のはざ間で朦朧としていたことがまだ最近のことのような感覚でいます。
でもあの大震災は1000年に1度だろうから生きている間にはもう同じようなことは身近にも海外でさえ起きないであろうと、みんなが確信していたはずです。そこに熊本地震…。倒壊した家屋の映像をニュースで見るにつけ、『ありえない。またか。地球は狂っているのか。』と思ったのは私だけではないと思います。しかし考えてみれば阪神淡路大震災、新潟県中越地震、岩手宮城内陸地震、東日本大震災、熊本地震と平成になってからだけでも甚大な被害をもたらした大地震が何度も起きています。いかに日本という国は地震という天災を肯定しながら生きていかなければならない国なのだ、ということを改めて思い知らされました。今回の地震で熊本市の大西市長さんも『今まで大きな地震を見聞きしたけれど、自分のことに当てはめることはできていなかった』と準備不足を口にしていました。まだ大きな地震に見舞われたことのない地方の方々は真剣に心と体制の準備をしっかりしてもらいたいと思います。そして九州地方の皆さんにはお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早く普通の暮らしに戻れるように心より願っております。
歯科医師の使命⑦
昨日は歯科校医をしている瀬峰中学校の歯科健診に行ってきました。一昨年度、歯科校医をしているということで栗原市の学校保健会から「あいさつ」という題で会報「けんこう」への原稿依頼があり第17号に掲載されました。学校歯科医としての自分の心情を書いたものですので今日はその文章を転載させていただきます。
* *
今から20数年前、宇野義方立教大学名誉教授(当時)著の「挨拶は怖い」を読んだ。そのころは歯科医院を開業したてだったので、スタッフに対する指導や患者さんへの対応の仕方を学ぶつもりだった。その中でまだ印象に残っているのは『自分から先に挨拶する』『形と心が伴ってこそ挨拶』と書いてあったことで、今でも何かにつけ思い出す。
私は学生時代硬式野球部であった。ご多分に漏れず先輩後輩の挨拶にはうるさかった。練習中はもちろん街で先輩を見かければすぐ近寄っては『ちゃす!!(こんにちは)』と言ったと思えばすぐ『失礼します!』と言って先輩が立ち去るのを見送った。当然後輩からも同様の扱いを受けた。その習慣が今でも抜けないので、知っている人だと気づけば寄って行っては声をかける。『自分から先に挨拶する』なのだ。声をかけられた向こうも挨拶を返さざるを得ないので、そこには相手をシカト(賭博言葉で無視)したとかされたとかという煩わしさが生じない。体育会の野球部と言えば確かに猛練習ばかりのいやなイメージしかないが、この点については役に立っている次第である。『体育会』なんてすでに死語であるが中学校などの部活ではそのようなことが踏襲されているのだろうか。しごきや暴力は困るが大きな声で人に挨拶することぐらいは覚えてほしい。そうすれば昨今の子供たちの一人でいるほうが楽だというコミュニケーション障害も少しは改善するのではないかと思うのは部外者の勝手な推測であろうか。
つまらない自慢話はさておき、われわれ学校歯科医と生徒が学校で直接挨拶を交わす機会はあまりない。唯一歯科健診で対面時に交わす程度であるがこれが極めて重い意味を持つ。健診時、私は生徒に向かって『こんにちは』と例によってこちらから先に声をかける。それに対しての生徒の反応がいかなるものかに全神経を集中させる。あらかた多くの生徒は『こんにちは』と返してよこすが、挨拶を返さない、目線もあわせない子が時折いる。おやっと思って口の中を見ると予想通り虫歯が異常に多い。抜歯すべき歯があったり歯周病にも罹患していたりする。もっとも虫歯が多くてもあっけらかんとしている生徒もいるが、往々にして挨拶がぎこちない子にはこういう場合は多い。
これはどういうことかと言うと、学校保健委員会などでよく説明させてもらっていることだが、虫歯の多くは後天的な生活環境によって発症、助長される疾患である。さらに口腔内の状況はその子の家庭環境、社会的背景も反映する。つまり口の中を見ることによってネグレクト、虐待、育児放棄といったことまで推測できることがある。アメリカでは歯科医が健診時に口腔内に極端な所見を持つ児童を診たら児童相談所に通報する場合があると聞く。
そもそもきちんと挨拶ができないとそこには心に何らかの問題、さらには家庭的、社会的な問題を抱えているのではないかと推測される。つまり『心が伴っていない』のである。そこから口の中を見る前に多発性の虫歯を必然的に予想することになる。
残念ながら学校における歯科健診とは口腔内の状態いわゆる事実のみを記録するだけである。そこに我々がなぜそうなったかの原因を探求することは求められないし、今後の対応を生徒に指示することもない。もともと健診票にはそういったことを記入する欄すらない。しかし職業柄、ほとんどの歯科医師は常に原因の究明と今後の対策を相当意識しながら健診している。口腔内が悲惨だと家での生活はどうなっているのだろうか、3度の食事はちゃんと取っているのだろうかと疑念を抱く。そしてこの思いをめぐらせる糸口になっているのが初めの挨拶と言うことになるわけだ。こういったことを鑑み、願わくはいつの日か健診時に全ての生徒さんが明るく大きな声で挨拶を返してくれることを祈っている。